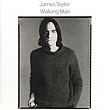70年代にアメリカ国内で隆盛を誇ったシンガー・ソングライターブームは、その土壌や地域性によってさまざまなスタイルを生み落とすに至った。主役はあくまでシンガーだが、フォークテイストのみならずジャズやソウルやポップスの素養を柔軟に備えた資質と、バンドアンサンブルによってもたらされる音飾効果やダイナミズムといったサウンドの洗練が、それ以前から続く自作自演のスタイルとの決定的な違いとなって表面化したのが70年代初頭。スタジオミュージシャンたちの手腕如何によってもアルバム全体のクオリティが左右する。まさにそんな時代の到来だった。
時を経て70年代後半、スタジオミュージシャンたち自身が主役になるというアルバムが一斉に制作され始める。クロスオーバーブームである。卓越した技術と洗練されたプロダクション、それに録音技術環境の進歩がそれまでにないクリーンでタイトな音像による心地良さを生み、彩るミュージシャンたちは一躍脚光を浴びる形になった。またAORと呼ばれる高い品質のサウンドが沸き起こるのもこの時期以降だ。しかし、平面的で引っ掛かりの少ないサウンドや、技術先行で自己顕示欲が強く表面化するその存在感がマイナスの印象をもたらした側面を孕んでおり、音楽的には高度な表現であっても一部のリスナーからは次第に敬遠されていった感も否めない。それゆえ“スタジオミュージシャン”という存在を偏見の眼差しで見る向きがあるのも事実だ。
しかしその直前、70年代前半にはそうした“退屈さ”とは無縁のサウンドがあった。シンガーのバックアップというスタジオミュージシャンの本来のあるべき姿がシンガーの持つ感性と互いに合い入れながら拮抗していた時期である。
シンガーとミュージシャンの人脈はアメリカ各地で独自の文化によって形成されていく。特に顕著なのは西海岸勢で、この地固有の特性からか数多くのアルバムが巣立っていった。では視線を東海岸に移すとどうか。そこにはまた違ったミュージシャンシップに裏打ちされた関係式や人脈図が見えてくる。
ニューヨークという都市周辺のスタジオミュージシャンといえば、スタッフ一派がその代表格だろう。数多くのNY制作のアルバムにクレジットされた、スティーヴ・ガッド、コーネル・デュプリー、ゴードン・エドワーズ、エリック・ゲイル、リチャード・ティーといった名脇役たちは、その存在感の大きさゆえオリジナルアルバムをリリースするまでに至った。彼らの主戦場はジャズやソウルといった黒人音楽系アーティスト周辺に近く、白人シンガー・ソングライターが演じるロック、ポップスといった世界でのサポート数は一気に減少する。白人シンガーをバックアップするミュージシャンといえばデイヴィッド・スピノザはその筆頭株主第一号だ。ギタリストとしてはもちろんプロデュース業にも名を連ねる才覚は日本では実はあまり評価されていない。70年代後半以降のフュージョンライクなカッチリとした音づくりの印象が強いが、70年代前半までのゴツゴツとした肌触りのプレイスタイルは一度聴くと病みつきだったりする。他にもラッセル・ジョージ(B)、エリック・ワイズバーグ(G)、ヒュー・マクラッケン(G)、チャーリー・ブラウン(G)、ラルフ・マクドナルド(Per)、スチュワート・シャーフ(G)、リック・マロッタ(Dr)、ポール・グリフィン(key)、アラン・シュワルツバーグ(Dr)など、結びつきの輪は途切れ途切れのようでいて、実は面白い形で繋がっている。カントリーやフォークをルーツに持つミュージシャンが多いのも特徴的だ。音そのものに個性が希薄という理由もあるだろうが、彼らの名がそれほど前面に際立たないという現実は、バックアップに徹するという本来の姿勢がこの時期確かに存在していたことの証拠でもある。そこには黒人・白人という区別はさほど意味はない。必要とされているのは上質のバンドアンサンブルそのものにあるのであって、必ずしも強固なリズムや柔らかいグルーヴの獲得だけが目的ではなかったからだ。
都市に集うシンガーたち。そして彼らの個性を支えながら“都会”が持つ固有の特性として互いに影響を及ぼしあうニューヨークのミュージシャンたち。あらゆる音楽の素養を抱えたさまざまなタイプのミュージシャンが集う地域性において、彼らが作りだす音楽には、他では見えにくい孤独さとその隙間から覗く屈折した光明が意図せず同居することに気が付く。スピリチュアルな主張を普遍的な日常の視線で表現する存在感を確かな音楽性でサポートするという構図。単なるアコースティックな感性だけではない、ジャズやソウルといった豊かな土壌を背後に備えたシンガーに演奏者たちも従順に反応するという進化は、黒人音楽の世界におけるニューソウルの流れにも通じる同時代性のようにも映るがどうだろう。
ただ、彼らの手によって形になった音像がすべて意図した通りに描かれたかどうかは疑問の部分もある。必要としたアンサンブルの実現が一方でぎこちなさを感じ取る結果をもたらす微妙なズレのようなもの。そもそもシンガー・ソングライターという存在がナイーヴな感性を持つ表現者なのだ。シンガーと演奏者の資質のギャップだと言ってしまえばそれまでだが、その違和感の所在は実に興味深い。
そんなクロスオーバーあるいはAOR前夜ともいうべき70年代前半に生み落とされたミラクルを以下にピックアップ。まあ地味です。世間的には見落とされた感もあるこれらアルバム群だが、それが主役の個性に起因するものなのか、サポートするミュージシャンたちの個性によるものなのかはともかく、まさに“見落とされていた”という文字通りの形容が相応しいと思えてくる静かなる素晴らしさにあらためて拍手を贈ります。そんなフォーキーでポップでソウルなバラエティに富んだ12枚をどうぞ。でもやっぱり地味かなあ。でもこの上なく素敵です。
|
|